カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>
毎週土曜日に配達されて来る、別刷りの日経プラス1(One)の「何でもランキング」。
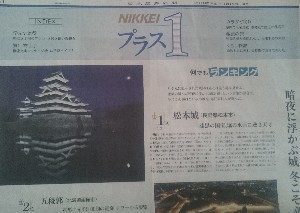

・「その均整の取れた姿は絵画を思わせ、雪の積もる夜は情緒ある光景が現れる」(夜景フォトグラファーの丸山あつし氏)
・「澄んだ空気の中で凛と佇む質実剛健名天守群は別格。時間を忘れる」(城郭ライターの萩原さちこ氏)
そして、説明文でも『400年以上風雪に耐えた漆黒の天守は別名「烏城」と呼ばれ、「白鷺城」の名を持つ姫路城と対比をなす。公園内の地面が堀の水面とほぼ同じ高さにあり、堀に「逆さ天守」が映り込む。』と、松本城の魅力を記してありました。さらに、『松本の住民らが修理を重ね、今も子どもたちが城内の床磨きをする』とも・・・。
「やっぱりなぁ・・・。さすが、分かってんジャン!」
と、些か(かなり?)“親バカ”的感覚ではありますが、松本市民としては「我が意を足り!」でありました。

 それにしても思い出すのは、城郭ライターの萩原さちこ氏が「松本城ほど市民に溶け込んでいるお城は無い」と評されていたのですが、その理由は、高校の先輩である“居酒屋評論家”大田和彦氏の、
それにしても思い出すのは、城郭ライターの萩原さちこ氏が「松本城ほど市民に溶け込んでいるお城は無い」と評されていたのですが、その理由は、高校の先輩である“居酒屋評論家”大田和彦氏の、「(見上げなければいけない平山城ではなく)松本城が平城であり、いつでも市民が自由にその周囲の公園に毎日の通勤通学時など立ち入ることが出来るが故に、日常的に市民の視線や目線の中に松本城があることが、市民から松本城が愛された理由だ。」と仰っていたのが、個人的にこれまでで一番納得出来た説明でした。また、以前TVの旅番組で、地元の市民の方が松本城を評して、
「松本藩の藩主は配置換えで次々と代わったので(注:初代石川数政以来、最後の戸田光則まで7代6家)、藩主さんには余り愛着が無い。だからその分お城に愛着を感じるのではないか?」
というのも、確かにそうだなと合点がいく気がしました。
だからこそ、市川量蔵から小林有也先生、そして現代の小学生に至るまで、松本城を市民の宝として大切に感じ大事にしているのだろうと思います。


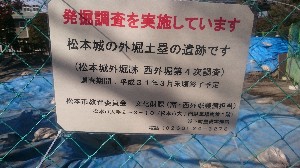

明治新政府からの廃城令により解体されて売られたりした全国の天守閣の多い中で、行政の力ではなく、市川量蔵等による市民運動で買い戻された松本城天守閣。地元の人たちの寄付だけで建設された旧開智学校同様に、そういう“市民運動”の土壌が松本にはあるのかもしれませんが、地元の“宝”だという彼等の先見性に感謝するしかありません。そしてその理由も、おそらく大田和彦氏の言われた「日常的に市民の視線や目線の中に松本城があった」からだろうと感じています。



