カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>
今年も一年間、本ブログ「三代目の雑記帳」をご愛読賜り、誠にありがとうございました。
果樹園のH/P開設と共に始めたこのブログも丸9年が過ぎました。
アクセス数も次第に増えて、6年前に年間15万件を数えました。しかし、ネタ切れと隔日での掲載に疲れ、二日おきのペースでの掲載とさせていただいた5年前には一時的に減ったものの、それでも12万件とほぼ毎月1万件というアクセスをいただき、その後は漸増して今年はこれまでの最高だった17万件を遥かに超えて、ナント22万件近い21万7千件ものアクセスを頂きました。
このページを借りて謹んで御礼申し上げます。ありがとうございました。


(今年最後の写真は、昨日の早朝ウォーキングでの、松本ウォーターフィールド付近から望む朝日に輝く常念岳と、今年もやっぱり東山魁夷の「年暮る」です)

来る2018年「も」、或いは「こそ」、皆さまにおかれましてもどうぞ良い年をお迎えください。
カネヤマ果樹園一同+ナナ
12月24日に京都で行われた、師走の都大路を駆け抜ける全国高校駅伝2017。
長野県代表の男子佐久長聖が2008年以来の優勝。そして女子は長野東が初の表彰台となる準優勝。これを快挙と言わずして、何でありましょうか。特に長野東は、必ずしも練習環境に恵まれているとは言えない県立の公立高校です。
佐久長聖は母校東海大の駅伝部監督に請われて転出した両角前監督がゼロから基礎を作り(監督自身が重機を操縦してクロカンコースを校内に造ったそうです)、その後は教え子の高見沢現監督に引き継がれていますが、昨年準優勝だった悔しさを晴らし、2008年以来2回目の優勝を遂げました。しかも、2008年の村澤・大迫等の“黄金世代”が作った日本人選手だけの最高記録以来の2時間2分台。近年は留学生がいるチームばかりが優勝している中で、最近では2008年の長聖以降、2010鹿実、2012山学大附属以来となる久し振りの日本人選手だけでの優勝です、
最近の長聖には、そうした方針や指導を慕って県内だけではなく近県からも優秀な選手が集まるようになりました。そうした中に静岡出身の佐藤悠や東京出身の大迫といったエースもいましたが、嘗ての“怪物”佐藤清治以降、上野、村澤、關、名取といった県内出身エースの系譜を引き継ぐ中谷選手の1区区間賞に始まり、一時は留学生に抜かれたものの、一年生が頑張って再度逆転し、最後は突き放しての優勝でした。
中でも2区区間賞の服部選手の面構えは良かった。走りも見事でした。彼は愛知出身。逆転した鈴木選手は静岡出身。更に栃木出身の富田選手に、今年は怪我で出遅れた我が中学の後輩である木村選手等、県内出身の優秀な選手も一年生にはいるので、来年度県内出身エースの系譜を引き継ぐべき松崎選手(塩尻出身)を中心に更に頑張ってくれるものと確信しています。
女子の長野東。昨年も和田選手の1区区間賞に始まり途中までトップを走っていたのですが、最終区でズルズルと順位を落として、過去最高順位の6位入賞とはいえ、チョッピリ後悔の残るレース展開でした。
今年は、主力選手の故障にもめげずに、1区和田選手の連続区間賞に始まり、2区の1年生高松選手が留学生には抜かれたものの、途中までトップに喰い付いて行く大健闘。そしてアンカー小林選手が最後のトラック勝負で並走していた選手を振り切っての見事な準優勝。3位以内のメダル獲得という目標を上回る準優勝で飾りました。「留学生がいなくても、公立高校でも頑張れば戦える!」。和田選手以外は一二年生。胸がスカッとした快走でした。
層が厚くなった成果とはいえ、駅伝は先行すると優位なだけに、和田選手という大黒柱が抜ける来年以降、如何に総合力を高められるか、或いはエースを育てられるか?小柄ですが、木曽の開田出身という高松さんに“女村澤”化を期待します。
明けて1月に行われる全国都道府県対抗駅伝。如何に中高校生を育てるかが、県内に社会人チームの無い長野県が全国最多優勝を誇るまでになった男子チームの強化ポイントでもありました。今年度も勿論優勝候補の筆頭でしょう。
そして、長野東の卒業生が大学・社会人で主力となりつつある女子チームも今年は期待できる!・・・そんな希望を抱かせてくれた快走でした。
佐久長聖&長野東の選手の皆さん、おめでとう!そして、感動をありがとう!
晩秋になると木々の葉も落ち、里山からは緑という色が消えてしまいます。“♪ もういくつ寝るとお正月~”という時期になり、街角からはお城にもう門松が飾られたという様なニュースも報じられていますが、冬でも枯れることのない松などの常緑樹の緑に永遠の生命を見て、子孫繁栄を願ったであろう日本の人々。その意味で“オモト”に“万年青”という漢字を当て嵌めた江戸時代の人々の気持ちも分からないではありません。
しかし、常緑樹の緑と謂えども、若葉青葉の新緑の頃の緑色とは、その瑞々しさが違う様に感じます。
以前もご紹介しましたが、エスキモーの人たちの言葉が「雪」を表す単語が世界で一番多いのと同様に、日本語には若草色や深緑など、緑を表す単度が世界のどの言語よりも多いのだとか・・・。芽吹いた跡の里山の様々な“緑色”を見る度に、それも「然もありなむ・・・」と感じるのです。

それは、大根。使った後の大根葉と根菜の部分を小皿などに浸しておくと、すぐに芽を出してすくすくと伸びて行きます。素晴らしい生命力です。

先述の自家製赤トウガラシは、乾燥用に100円ショップで見つけた根菜用の網目の保存袋で代用したのですが、実際は乾燥用の器具が売られています。
それは“ハンギングネット”という名称で販売されている「一夜干し」用の網の籠。
ネット検索をすると、キャンプ用品などで使われることが多い様で、サイズにも依りますが、アウトドア用品で知られるブランドのモノだと3段のネットの籠で大体1500円前後でしょうか。

目的は赤トウガラシ乾燥?・・・左に非ず!で、“干し芋”作り用なのです。
昔懐かしい“干し芋”、或いは“芋干し”。昔我が家では、祖母が(サツマイモは自家製だったかどうか記憶が定かではありませんが)蒸かしたサツマイモを切って天日干しにして自家製の“芋干し”を作っていました。お餅を薄くスライスして天日干しにしたモノを茅葺の家の囲炉裏で、油で揚げたり、炒ったり(炙ったり?)して、やはり自家製の揚げ餅やあられを作ってくれましたから、昔は今で云うスナックも全て自家製だったような気がします。
干し芋/芋干しは茨城県が主産地ですが、奥さまに由れば、次女が成田に住んでいた時に成田山新勝寺の参道にあった名物の落花生と並んで売られていた“干し芋”が柔らかくて甘くて忘れられないとのこと。
羽田に移った今は、成田で購入出来ないことから、我が家の冬の“風物詩”である薪ストーブで作る焼き芋を使って、“干し芋”を作ってみることにしました。それも、家内が薪ストーブで作った焼き芋が、たまたま余り美味しくないと食指が伸びずに冷蔵庫に保管されていたので、ホンなら試しに干してみますか・・・となった次第。

「旨い! これって、昔の芋干しだぁ。いやぁ、懐かしいなぁ・・・!」
素人でもこんなに簡単に作れるなら、だったらチャンと作ってみようということになり、乾燥させるための“器具”を探して購入した次第です。今回は、ネットではなく、地元のホームセンターでちゃんと見つけることが出来ました。
この“ドライネット”(ハンギングネット)はトウガラシや干芋用にだけではなく、例えば魚の干物作りにも勿論使えます。今では流通網も昔に比べれば発達し、山国信州でも新潟などから朝採れの魚が店頭に並ぶ時代ですので、豊漁で安い時に鯵や鰯などを生で買って捌いて一塩振ってこのネットに入れておけば、新鮮で安い“一夜干し”などの魚の干物が、この山国信州でも自家製で楽しめるかもしれません。
我が家での干し芋は、本来の蒸かし芋ではなく薪ストーブで作った焼き芋ですが、その後奥さまは喜んで、残った焼き芋を使ってせっせと?自家製の干し芋作りに励んで?います(私メが買ってくるモノは評判が悪く、無駄遣い扱いされることが多いのですが、このドライネットは久し振りにお褒めに預かった次第・・・です)。
昨年、奥さまのお友達からいただいた自家製の赤トウガラシ。たくさんは要らないがあれば重宝すると云うので、今年の家庭菜園に一株だけ赤トウガラシを植えてみました。
春先の夏野菜の苗購入と併せて、高校の同級生の経営するいつもの園芸店「ナカツタヤ」で、スタッフの方から、並んでいた中で一番辛いという種類(鷹の爪の一種)を選んでもらってポット苗で購入したものです。

既に20個以上になり、家庭で使うには十分な量です。優に数年分はあります。この段階で、まだ株には50個ほどが“鈴なり”になっていました。


一番辛い種を使わずに細いのがたった一本ですが、これは辛い!
(後で知ったのですが、赤く熟しtモノより青い方が辛いのだとか)
植えたのは一株だけでしたが、全部で70本以上にもなりましょうから、全て乾燥させれば恐らく10年分?くらいにもなるでしょうか・・・。
 日当たりの関係か、他の市民農園に植えられていたトウガラシに比べると、我が家の一株も次第に赤味を帯びて来たものの、降霜時期の11月まで待っても全て赤くはなりませんでした。
日当たりの関係か、他の市民農園に植えられていたトウガラシに比べると、我が家の一株も次第に赤味を帯びて来たものの、降霜時期の11月まで待っても全て赤くはなりませんでした。そこで、やむなく引き抜いて葉を落とし、逆さまにして干しています。それでも、真っ赤く熟したモノだけで優に30本くらいはあるので、もし緑色のモノが利用出来なくても、合わせて50本以上と十分過ぎる収穫量です。作っては見たモノの、どうやって利用すれば良いのでしょうか。
京都に行ったために今年は参加出来なかった“松本歴史ウォーク”の代わりに、タウンペーパーに案内があって参加した“中山史跡ウォーキング2017”。先月末の11月25日に行われました。

主催は地元の地域づくりセンターで定員50名とのことでしたが、当日集合場所の中山公民会には30名程度の皆さんが集まっておられました。我々の様な中高年層が中心です。
朝8:30分に受付をして、最初に主催者からの挨拶や注意事項の説明、準備体操をしてから9時にスタート。松本歴史ウォークなどと違い、途中ポイント毎に市教育委員会のOBの先生や地元の方々からその史跡の説明を伺いながら、参加者全員がゆっくりと縦列になって一緒に歩を進めます。


そして、中山霊園の最上部付近から中山北尾根の遊歩道を通って、尾根の先端部分にある弘法山古墳に向かいました。
この北尾根。僅か2㎞とはいえ、緩やかな下り道では無くて結構なアップダウンがあり、市街地からほど近いこの場所にこんな本格的なトレッキングコースがあったとはビックリしました。

そこから、弘法山の下にある「泉小太郎」の像(この地を流れる和泉川に由来するとの地元に伝わるそうです。同種の民話はそこらじゅうにありますが・・・)から、地元の溜池である生姜池(松本藩から諏訪高島藩へ藩領が移された際に、これまでの様に松本藩から用水を取水出来なくなったために造られた農業用水とのこと)などを通って地区のセンターで昼休憩。そこで地元の愛好団体の方々が休耕田を利用して育てている蕎麦で打った本格的な新そばを昼食にいただきました。


 “中山史跡ウォーク”。今回で7回目だそうですが、「霊園だけではない」中山地区を知ってもらうために、今回初めて地元以外の市民にも参加を呼び掛けたのだそうです。
“中山史跡ウォーク”。今回で7回目だそうですが、「霊園だけではない」中山地区を知ってもらうために、今回初めて地元以外の市民にも参加を呼び掛けたのだそうです。設定されたスポットを回りながら20km近いコースを歩く松本歴史ウォークや梓川ウォークと異なり、ウォークラリーとしては7kmと短く、またとてもゆっくりとしたペースで参加者が一緒に歩きますが、ポイントポイントで歴史的な説明が聞けるので、ただ黙々と歩くよりも(氷雨の中の梓川ウォーク18㎞は辛かった)個人的にはむしろ楽しめました。
考古館長さん曰く、「埴原城など、他にも中山地区には面白い所がありますよ」
とのこと。今回とは違う歴史スポットを廻るようであれば、また是非参加したいと思います。
京都での最終日。午後の移動なので、午前中に願掛けのお参りに行くことにしました。自分たちでは無く、親バカながら当然子供たちのためのお願いです。神社も多い京都ですが、今回の参拝は下賀茂神社。以前家内のご友人から下賀茂神社のお守りを子供たちにいただいており、今回は直接お参りしたいとのこと。
そう云えば、京都での学生時代も、お寺はたくさん回ったのですが、神頼みをしたくなかったのか、神社は殆ど回っておらず(せいぜい京都のシンボルである八坂神社くらいでしょうか)下賀茂神社も近くは何度も通っているのですが、参拝するのは自身初めてです。
ホテルのチェックアウト時間までに戻れる様に朝7時に出発。バスで河原町今出川へむかいました。




「じゃあ、東寺に行って見よう!」
学生時代、私メは東から“上洛”していたので、東山トンネルを抜けるとすぐ左手に清水寺などの東山が見え、京都タワーが見えると「さぁ、着いた」と認識に、ホームに降りて目の前に聳える東寺の五重塔に「あぁ、京都だなぁ・・・」。京都タワーと共に、東寺の塔が京都のシンボルでもありました。


 勿論、明るい博物館で貴重な“文化財”として拝見出来る仏さまも良いのですが、やはり御仏は、我々民衆の祈りを千年以上にも亘りじっと受け止めて来られた崇拝の対象として、現代においても本来鎮座される薄暗いお堂の中でこそお会いして、そして静かにお祈りすべき存在なのだと感じました。
勿論、明るい博物館で貴重な“文化財”として拝見出来る仏さまも良いのですが、やはり御仏は、我々民衆の祈りを千年以上にも亘りじっと受け止めて来られた崇拝の対象として、現代においても本来鎮座される薄暗いお堂の中でこそお会いして、そして静かにお祈りすべき存在なのだと感じました。見返り阿弥陀さまにお会い出来なかったのは残念でしたが、久し振りの京都を楽しんだ4日間でした。
京都駅の新幹線のホームから見える東寺の五重塔に見送られて、古都を後にしました。
京都を散策したり、食事に行ったりした時に思いがけず出合った我が懐かしの京都。
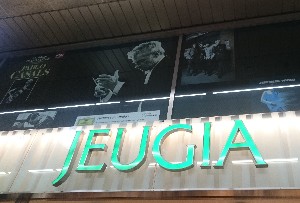


「あぁ、あの頃と同じ場所、同じ建物で、まだちゃんとしっかり営業してたんだ!」
と、実に感慨深いものがありました。実際は、会社も発展したようで、暫く歩くともっと大きな販売店舗があり、従業員の方々が何人も働いていて、あの懐かしい焙煎する芳しい香りが漂っていて、一瞬40年前にタイムスリップした様でした(旧店舗はどうやら倉庫か何かに使われているようです)。
そして、バス停の府立病院前。以前は「広小路」。既に立命館の広小路学舎はありませんが、府立医科大に当時の懐かしい建物が残っていました。

そう云えば、京都人の友達に教えてもらった通りの名前の数え唄・・・“♪ まる たけ えびす に おし おいけ~、 あね さん ろっかく たこ にしき ~、し あや ぶっ たか まつ まん ご~じょう ”。これは東西の通り名ですが、(本来の)お上りさんにとっては大変分かり易かった記憶があります。通りの名前を確認しては「あっ、なるほど!」と納得したものです。
今回も丸太町から南方向へ歩きながら、
「そうだ、押小路から下がるから次が御池だ!」
などと、何となく昔の感覚(≒たったの4年間とはいえ、京の都に住んだ人間としてのプライド)が少しだけ蘇って来た様な気がしました。

東京での仕事を終えて、大きなスーツケースを引いて前日の夕刻京都へ来た長女を京都駅で出迎え。
翌朝、時差もあってか娘が早くに目覚めたので、外は予報通りに生憎の雨模様でしたが、小雨だったので皆で早朝ウォーキングへ出掛けました。こ
の日も平安神宮から哲学の道へ向かい、紅葉の永観堂から南禅寺へ。京都でも仕事で観光どころではないであろうことから、紅葉の京都をホンのひと時ですが楽しんでいました。午後のアポイントまでに半日だけ時間が空いていると云うので、雨でさえなければ東山界隈でも観光に廻れるのですが、天気が悪く諦めてホテルで少しノンビリしてから、娘の重いスーツケースを今晩のホテルの近い京都駅の八条口に預け、娘が予約をしてくれた祇園の元お茶屋さんへランチに向かいました。


「夜はともかく、昼はとってもリーズナブル。南禅寺の“湯豆腐”のコースとお値段はそんなに変わらないから大丈夫だよ!」
おカタジケ!・・・でありました。先付けに始まり、八寸、お造り、焼き物、汁椀等が御膳にキレイに並べられています。
以前ご紹介した平松洋子女史曰く、伏見に代表される様に、京都が軟水故に発達したと云う出汁文化の京料理。舌だけでは無く目でも味わえた御膳。部屋からは京の町屋らしくしっとりした坪庭が眺められ、ゆったりと食事を楽しむことが出来ました。「津田楼」にはバーカウンターもあり、お酒だけでも楽しめる様です。

そこで、寺町二条の京都市や区穂近くにある一保堂茶舗嘉木へ行くことになりました。

旨味というか、甘味のある煎茶。何より驚いたのは注いだ後の茶葉の色。夏の茶摘みの頃を想わせる様なキレイな緑色です。
「食べることも出来ますよ!」
という説明に、思わず口に含んでみました。確かに茶飯もありますから・・・。

その日のアポイントに行く長女とはそこでお別れです。
「体に気をつけて、あんまり無理しない様にね。」、「頑張れよ~!」
「今度は西海岸へ行くからね~!」、「ん・・・?」
京都初日の夜。奥さまの意向は一切確認せず、私メだけの希望で場所を決めてありました。それは新京極にある「京極スタンド」です。昭和2年創業と云うレトロな食堂であり居酒屋でしょうか。元々は十銭食堂とか。店の存在そのものは知っていましたが、学生時代も何となく来たことはありませんでした。
まぁ、新京極自体がお土産購入目当ての修学旅行生の闊歩する(修学旅行生同士の小競り合いやケンカが当時は日常茶飯事だった様な)イメージですので、京都の学生が目的的にあまり来る様な場所では無かった気がします。


オーダーは、京都なので湯豆腐、名物のコロッケ、鱧の天婦羅と揚げそば。はんなりでは無く関西風に元気の良いオバサンの店員さんから良く通る声で都度オーダーが通されます。


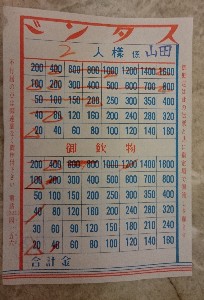

お店は満席で、こちらのお腹も一杯になったので早めに席を空けることにしました。年代物の古びたレジスターも何とも良い雰囲気です。決して“はんなり”という様な京都らしい店では無いのかもしれませんが、古き良き昭和の雰囲気と、学生を“学生さん”と呼んで可愛がってくれた京都らしい優しさが残っているような、きっとこんな店だったら店員を怒鳴りつけて土下座を強要するようなクレーマーの様な客も生まれないだろう、そんな感じのするどこか暖かで居心地の良い“大衆食堂”でした。



