カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>
米国ではサラダ用に大変ポピュラーだと知ったケール。
サラダに使われるのは、通常の葉の硬い青汁用とは異なり、パセリの様な葉をしたカーリータイプのケールで、葉が柔らかく生食に向いています。


カーリーケールはアメリカで食べたモノよりジャミジャミ感が無く、むしろ柔らかい気がします。でも、味はしっかりケールの味。

『・・・食物繊維が豊富で、抗酸化ビタミンやカルシウム、βカロテン、ミネラル、葉酸、たんぱく質が豊富に含まれています。特にβカロテンはなんと、トマトの5倍!カルシウムは牛乳の2倍含まれています。葉酸は妊娠中に摂りたい栄養素でサプリメントで補う場合が多いのですが、自然の食べ物から摂れたら安心安全。そんな葉酸もケールにはしっかり含まれています。また、快適な睡眠を得るために重要なメラトニンも沢山含まれているんです。そのため、不眠症の改善に役立つ効果が期待されています。そのため、ケールは「野菜の王様」と呼ばれています。・・・』
とのこと。青汁だけではなく、生食で食べられればそれに越したことはありません。米国で(健康志向の人たちの間で)サラダ食材として盛んに食べられているのも大いに納得出来ます。
夏野菜の代表である茄子(ナス)。
長ナスや水ナスなど、色々な種類がありますが、我が家を含め、昔から松本地方で良く栽培されているナスは長卵形のナス。野菜苗で売られている最近のナスで代表的なのは、「千両」というタキイ種苗の種類でしょうか。
漬け物に良し、油との相性も良いので揚げたり焼いたり煮たりと、色々な料理に使われています。そうした中で、信州では「ナスのお鉄火」と呼ばれる家庭料理、鉄火味噌のナス炒めがポピュラーです。そして、お焼きとしても、炒めた野沢菜(これは本来漬かり過ぎて酸っぱくなった野沢菜漬けを使うので、時期としては春先の具材)や切干大根などと並んで代表的な具材(「ナス味噌」との表記もあり)でしょう。



サイトウキネン音楽祭から名称を変えたセイジ・オザワ松本フェスティバル(OMF)。妹の勤務先がスポンサーとのことでチケットを頂き、8月18日に行われたサイトウ・キネン・オーケストラ(SKO)による最初のオーケストラ・コンサート(Aプロ)を聴きに行って来ました。

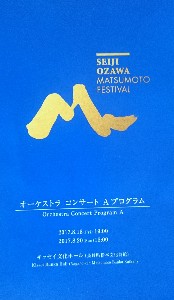 久し振りに聴くSKO。前回が大好きな十束尚宏さんも振られた“20周年記念演奏会”だった筈なので、5年振りでしょうか。この日がメインのオーケストラコンサートの開幕なので、ロビーは華やかさが溢れています。
久し振りに聴くSKO。前回が大好きな十束尚宏さんも振られた“20周年記念演奏会”だった筈なので、5年振りでしょうか。この日がメインのオーケストラコンサートの開幕なので、ロビーは華やかさが溢れています。それにしても4年連続で客演するファビオ・ルイージ氏。SKOとの相性の良さが評判ですが、某音楽評論家曰く、どんな実力ある指揮者でも、昔のカラヤンの様な絶対的君主や練習が厳しい指揮者は今や好かれず、民主的でオーケストラ団員に好かれることが指揮者としては最も重要なのだとか。
メトロの首席指揮者などを歴任したマエストロの実力は勿論ですが、団員に好かれていることがSKOとの相性の良さに表れているのでしょうか。
一見、有能なバンカーの様な雰囲気ですが、やはりそこはイタリア人のマエストロ。寄せては返す、押しては引く波の様に自由自在で、そして想像以上に情熱的な指揮振り。名手揃いのSKOの反応も凄い・・・。この日のコンマスを務められた矢部達哉さん以下、SKOの厚みのある弦の巧さは定評あるところですが(ヴィオラ首席の川本さんのソロパートも艶やかでとても素敵でした)、それにしても管楽器の上手い事といったら唖然とする程でした。それもその筈で、バボラクさんのホルンを初め、有名オケの首席クラスが各パートに揃っているのですから。それにしても、感動よりも感心して溜息と共に呆気にとられておりました。
「はぁ~・・・、ホントに巧いなぁ・・・!」

何度ものカーテンコールの後、団員も客席に深々と一礼してからお互いを称え合い袖に引き上げても拍手は鳴り止まず、やがてそれに応えるように指揮者を始め全員がステージに再登場。10分以上も鳴り止まぬ盛大な拍手に応え、何度かのお辞儀の後、一人ひとり手を振りながら退場し、漸く我々聴衆も退席しました。
母のショートステイ期間中に合わせて、お届けモノの荷物を運びがてら、車で娘の所に上京しました生憎、都会に近付くにつれての雨。慎重に運転しながら、ゆっくり走って談合坂で昼食がてら休憩し、ここで“都会に慣れた”談合坂で奥さまに運転を交代。幸い平日故に首都高も然程の渋滞も無く、予定通りに羽田ランプで高速を降りて、最初に娘の住むマンションへ荷物を届けてからいつも通り大鳥居のホテルへ。

江戸小路は「朝顔市」風の夏の装い。何だか、ここに来た方が“日本の夏景色”が感じられます。
蒲田の餃子をあきらめたためか、今回は中華で飲茶を何品かと私メは餡かけ焼きそばと奥様は中華風冷麺。上品な味で美味しゅうございました。



その後で表参道で奥さまと合流し、一緒に糀谷に行ってから松本へ向かいました。
お盆に来られた県外からのお客様をご案内して木曽路へ。
松本から、信州らしい観光を兼ねて昼食となると、天候に左右される高原や山などの景勝地は夏はリスクが高いので、(松本を除けば)木曽の奈良井宿か上田の別所温泉(「信州の鎌倉」)。今回は久し振りの木曽の「時香忘」の蕎麦と奈良井宿をご案内することにしました。

 奈良井観光を後にして先に木曽福島の「時香忘」目指しました。ところが・・・です。駐車場に車の姿は無く、
奈良井観光を後にして先に木曽福島の「時香忘」目指しました。ところが・・・です。駐車場に車の姿は無く、「えっ、定休日???」
入口の張り紙曰く、ナント「オーナー夫婦の体調回復までの間、定休日を大幅に変更します。8月は日曜日と11日から20日までお休みします。」とのこと。続けて、「先2ヶ月の定休日を食べログに掲載しております」との記載。
「オイオイ、食べログは嫌いで見ない人だっているでしょうがっ!!」
本来であれば自身のH/Pで告知すべきでしょうが、もしH/Pが無いとしても、「食べログ」だけに告知すると云うのは、お客様商売としてはあまりに不親切ではないでしょうか?しかも、「店は関係ありません」の様な何とも第三者的な書き方は一体何?奈良井から往復1時間の無駄なドライブをお客様にお詫びし、奈良井宿へ戻りました。


元の会社の後輩たちとの、年に一度の松本での食事会。
元々は松本のB級グルメからスタートしたのですが、田舎では限られてしまし、一年前の定年退職時の激励会のお礼も兼ねて、今回は我が家での“インドカリーを食す会”。松本市中には北インド料理の(お酒と一緒に、サモサ、タンドーリチキンなどの前菜に始まりガラムマサラ各種を味わえる様な)レストランが無いため、郊外の“エスニック風”のレストランを車で巡ると運転手が飲めませんので、(飲むためにも「じゃあ、ウチで食べよう!」と相成りました。
最初は、奥さま手作りのシンガポール・チキンライス(海南鶏飯)とタイ・グリーンカレーと思ったのですが、自家製野菜を使ったサラダやプルスケッタなどの一品料理が追加された結果、食べ切れないからと、カレーを何種類か用意することにしました。

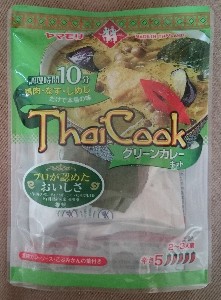 無印のインド風カレーは、もう少し辛味と甘みが強調されても良いかと思いましたが、他にも辛味の強いスパイシーチキンなどもありましたので、自分好みの味を探してみるのも良いかもしれません。但し、一般のレトルトに比べると些かお高めの価格設定ですので、試しに自分で調理するバターチキンのカレーキットも合わせて購入してみました。
無印のインド風カレーは、もう少し辛味と甘みが強調されても良いかと思いましたが、他にも辛味の強いスパイシーチキンなどもありましたので、自分好みの味を探してみるのも良いかもしれません。但し、一般のレトルトに比べると些かお高めの価格設定ですので、試しに自分で調理するバターチキンのカレーキットも合わせて購入してみました。奥さまの作った何種類かの一品料理に加え、3種類のカレーに合わせるのがタイのジャスミン米なので、更に現地風で美味。お陰さまでお客様にも大好評で、「次回の設定はシンガポール・チキンライス(海南鶏飯)を是非!」とのリクエストを頂いてお開きとなりました。
「ホンジャ、またネ!」
今年は、奥さまから自家用の野菜もちゃんと作って欲しいと厳命されたため、果樹園横の畑スペースに数年振りに野菜を栽培しています。
先ず畑を耕すことから始めないといけないのですが、暫く使っていなかったためトラクターがバッテリー上がりで動かず。小型の耕運機もエンジンが掛からず・・・・とトラブル続き。
そこで、農協(JA)の支所(経営効率化の一環で、昨年岡田と本郷支所が統合され、新たに女鳥羽支所として発足)に耕運機を軽トラに積んで運び、部品交換等も含め一週間程掛かりましたが修理をしてもらいました。
また、トラクターはバッテリーを外して同じく支所に持ちこんで充電してもらいました。ところが、今度はタイヤの空気が抜けていたので、いつも行く知り合いのスタンドに相談し、エアタンクを貸してもらって自分で充填しました。
そして、伸びていた雑草を刈り取り、浅くトラクターで起こしてから雑草の根を4本鍬で取り除いてから、苦土石灰を撒いて再度トラクターで今度は深く起こします。そして、次に耕運機で土が細かくなる様に何度も往復して耕します。そして、鋤などを使って畝を何本か造り、必要な部分を雑草除けと乾燥防止のためにマルチシートを張って畝を覆います。農家で有難いのは、祖父や父時代からの農具や農業資材、肥料が(探せば)全て揃っていることでしょうか。
栽培準備をした上で、いつもの同級生が営む地元の老舗の「ナカツタヤ」から今年もポット苗で購入。
キュウリを6本、トマトを5本、ナスも5本。加えて今年はカボチャとオクラも2本ずつ。友人からいただいた小ネギ40本も一本ネギとして育てるべく、畝を立てて植えてみました。またトウモロコシ(スイートコーン)とインゲン(つるなしタイプ)は種で購入し、ポットで育苗してから移植。
大根はもう上田に行く機会が無いことから、今年は自分で辛味大根を育てることとし(但しネズミ大根は坂城町から門外不出)、奥さまのリクエストで地元で「硬大根」と呼ぶ信州地大根も種で購入。辛味大根だけは早めに植えてみました。地大根は秋の収穫前提で夏植えになります。


色々探してみると、青汁用ケールだけでは無く、トキタ種苗の「カリーノケール・ミスタ」というフリル形状の葉になるカーリーケールの種を発見。生食サラダ向きとの記載もあり、何でもヴェルデ(緑)とロッソ(紫)の2種類の種子が入っているとのこと。早速ポットで育苗し、本葉が2~3枚になったところで移植してみました。




この前初めて収穫して、サラダにしてみましたが、米国西海岸で食べたケールと同じ食感と味でした。これ、サラダに絶対お薦めです。日本でも人気になるかもしれません。
最近、新聞などで時々目にする耳慣れない言葉、“オノマトペ”。
一体ナンジャラホイ?と気になって調べてみると、日本語では「擬声語」とか。だったら、そう言ってくれれば分かり易いのに、と思うのですが、所謂「ワンワン、ニャーニャー」といった動物の鳴き声や、「しくしく」とか「ズキズキ」、或いは「しとしと」「しんしん」といった状態を表す言葉のことだとか。
語源は古代ギリシア語で、英語では“onomatopoeia”という単語があるにも拘らず、カタカナで最近目にする「オノマトペ」は“onomatopée”という綴りのフランス語なのだそうです。
特に最近注目されているのは、医療現場で、患者さんの痛みをより正確に把握するのに、このオノマトペが有効なのだとか。通信回線を使った遠隔医療の発達などがその背景にはあるようですが、ナルホドと思い至ったのは、シンガポール赴任時で、一番厄介だったのはお医者さんとの会話。子供を病院に連れて行って診てもらう時に、具合を正確に伝え切れないもどかしさを痛感しました。ですので、在住の外国人の方がますます増えていく中で、医療現場で症状を表すのに、そうした擬声語が、出来れば将来的に世界共通に標準語とされれば便利だろうと思います。
この“オノマトペ”。医療現場のみならず、チビリチビリ、フワフワなど、料理の状態や美味しさなどを表現するのにも随分有効だと思います。その意味で、料理界での“オノマトペ”の達人は、何といっても以前日経新聞に連載されていた『食うあれば楽あり』でお馴染みだった醗酵学者の小泉武夫先生ではないでしょうか。ジュルジュル、ぴゅるぴゅるなど、正に小泉流“オノマトペ・ワールド”全開といった趣でした。
家を建ててから20年。家も“勤続疲労”で色々ガタも来ており、ギシギシ音を立てていた玄関ドアの補修や雪害で壊れた雨樋の補修など、プチリフォームをお願いしました。その際足場を組んだこともあって、この際もう寿命の来ていた薪ストーブも交換しました。
薪ストーブも家を建てた時に入れましたので、勤続20年。
高齢化に従い薪運びも大変かも・・・と、最初はペレットストーブも検討してみましたが、間伐材活用で裁断して固形化するペレット製造に自治体が補助をしているので、ペレットそのものの調達コストが将来的に不安要素となりうることもあって、結局ペレットよりもシンプルな薪ストーブにしました。FF方式のペレットにすると排気ダクト等の工事が必要になりますが、薪ストーブならそのまま今までの煙突も(利用可能であれば)使えます。


それにしても、「ピアノよりは楽ですよ」と笑っておられましたが、重機を使わずに(使えずに)人力で100kgを軽く超えるストーブを設置するのは大変な重労働だと感心した次第。
3時間近く掛かって古いストーブを撤去し、新しいストーブが設置されました。モダンなストーブがリビングに据えられ、何だかリビングルームの雰囲気も一変したような気がします。
 20年ほど前に家を新築した際、吹き抜けのリビングの強度確保のための柱を活用して設けられた飾棚。両側がガラス扉になっていて、奥さまがシンガポール赴任中に買い集めた陶器やクリスタル製品などの収納を兼ねて飾られています。その下はオーディオラックを兼ねたウッドボックスで、こちらは機材やケーブル類が見えない様に木の扉で覆われています。因みに、以前もご紹介した様に設計士さんにお願いして、スピーカーケーブルも床下を這わせて壁側とウッドボックス内から出してスピーカーとアンプを繋げているので、邪魔なケーブルが床や壁を這わせるなどということはなく、実にスッキリしています。
20年ほど前に家を新築した際、吹き抜けのリビングの強度確保のための柱を活用して設けられた飾棚。両側がガラス扉になっていて、奥さまがシンガポール赴任中に買い集めた陶器やクリスタル製品などの収納を兼ねて飾られています。その下はオーディオラックを兼ねたウッドボックスで、こちらは機材やケーブル類が見えない様に木の扉で覆われています。因みに、以前もご紹介した様に設計士さんにお願いして、スピーカーケーブルも床下を這わせて壁側とウッドボックス内から出してスピーカーとアンプを繋げているので、邪魔なケーブルが床や壁を這わせるなどということはなく、実にスッキリしています。




「あぁ、どうしてもっと早くこうしておかなかったんだろう!」
と後悔しきり・・・。遂に20年来の念願が成就して(≒積年の恨み辛み?を晴らすことが出来て)、大いに満足した次第です。
(小せぇ、小せぇ・・・って、フン、放っといてください!)
6月に入って、ポット苗を買って来て恒例のハーブガーデンに移植しました。
今年は、奥さまから「自家用の野菜もちゃんと作って欲しい」と厳命されたため、果樹園横の畑スペースに数年振りに野菜をも植えることにしました。従って、ガーデンスペースの一部、一坪ほどの狭いハーブガーデンへは、今年は野菜は植えずにハーブのみ。そのため、例年の倍のハーブを植えることが出来ます。二月にストーブの木灰を撒いて鋤込んであります。
プランターを含め、植えたのは、パセリを2株と、多年草ですが3年目の今年は枯れてしまったので再度セルバチコを2株。定番の、バジルを5株にコリアンダーが5株と、ルッコラが4株。そして、屋根下で雨が掛からない部分には今年もミニトマトとフルーツトマトを一株ずつ。多年草のチャイブは、今年も元気に生えています。






