カネヤマ果樹園 雑記帳<三代目のブログ>
小学館から毎月2回発刊されてきた、全50巻のクラシックプレミアム。
魅力は高音質のSHM-CDで、発売当時話題となった往年の“ベスト盤”中心に構成され、中には私の学生時代には既に定評のあった嘗ての名盤も含まれていることでした(第830話)。そして、この11月末を以って2年間に及んだ全50巻の配本が終了しました。

例えば、43歳の若さで夭逝してしまった、イシュトヴァン・ケルテスの出世盤となったVPOとの「新世界」。これは54年前の1961年の録音。若きケルテスが名門VPOと対峙した、情熱溢れんばかりの熱演で、当時から名演と評判の高かった録音です(その後もVPOとの良好な信頼関係を築きながら、ケルテスの突然の事故死で未完となったブラームスの交響曲全集に収録するハイドン・バリエーションの終曲パッサカリアを、VPOが氏の追悼のために指揮者無しで録音したのは有名なエピソード)。驚くべきは、例えばティンパニーの超ド級の迫力。(それなりの大音量で聴いていたこともありますが)度胆を抜かれました。個人的には、超優秀録音(普通のCDです)だと思っている2008年のオザワ&SKOの「巨人」のライブ録音の、特に第4楽章でのティンパニーにも匹敵するほどでした。このVPOとの「新世界」の評判により、ケルテスは後年首席指揮者となったLSOとも全曲録音します(その7番と8番「イギリス」のLP、そしてVPOとのモツ・レクのCDが手許にありました)。
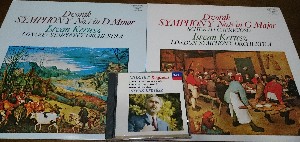
この「幻想」も、管楽器を初めとするオケ自体の旨さと新生パリ管としての意欲も手伝ってか、天才ベルリオーズが描いた、この曲の持つ天使と悪魔のような“豪華絢爛的狂気さ”(変な表現ですが)を描き切った名手ミュンシュの演奏自体の凄さに加え、1967年という、やはり50年近く前の録音とは思えぬ程の音の良さでした。
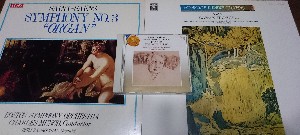
時代遺産としての演奏そのものは(例えSPやモノラルであっても)色褪せぬとも、今回の“マスター音源に限りなく近い”というSHM-CD化により音質が飛躍的に向上し、改めて輝きを得て現代に蘇ったようで、ハイエンドでもない古い装置(当時の中級機で構成したオーディオ装置と自作スピーカー「スワン」)で聴いているオーディオファンとしても大いに満足出来ました。

そして、個人的に一番の収穫は、これまで“聴かず嫌い”だったであろう、シューベルト「ザ・グレイト」(晩年のベーム指揮SKDのライブ録音。第863話)の素晴らしさを知ったことでしょうか(一度生で聴きたいと思います)。


(また何か、オーダーしようかな・・・うーん、志ん朝か談志の名演集とか・・・?)



